【実機レビュー】ドリル研磨機で切れ味復活!使い方とメンテナンスガイド

業務でもDIYでも金属加工に欠かせないドリル。しかし、使っているうちに切れ味が落ちたり、時には先端が欠けたり折れてしまったりすることもありますよね。
「切れなくなったドリル刃、どうしていますか?」
「折れたドリルを、諦めて捨てていませんか?」
グラインダーでの手研ぎに挑戦しても、熟練の技術が必要です。時間と労力をかけたのに、結局切れ味が戻らない…なんてことも。
そんな悩みを一挙に解決してくれるのが「ドリル研磨機」です。
今回は、Amazonで本格的なドリル研磨機「Huanyu 13A」を購入しました。
この記事では、数ある製品の中からなぜこの機種を選んだのかという理由から、切れ味が落ちた刃はもちろん、折れたドリルの再生まで、実際の使い勝手や研磨効果を徹底レビュー! 使ってみて分かった良い点・注意点まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます!
目次
なぜ、ドリル研磨機が必要だったのか
購入に至った背景
私が以前、広島で勤めていた職場にはドリル研磨機があり、その圧倒的な便利さを実感していました。現在の職場では、ガイドを使って下穴なしで穴あけをすることがあり、ドリルの食いつきを良くする「シンニング加工」が不可欠な状況でした。
シンニング加工とは?
ドリルの先端中心にある切れ味の鈍い部分(チゼル)を研磨し、食いつきを向上させる加工のこと。
特に困っていたのが、穴を貫通させずに掘り込むだけの作業です。適切な刃先形状でなければ、ドリルが狙った位置からズレてしまう「歩行現象」が発生し、穴の形がいびつ(三角形や五角形など奇数形)になってしまいます。
これまでは切れ味の落ちたドリル刃は、グラインダーを使って手作業で研磨していましたが、シンニング加工を正確に行うのは至難の業でした。チゼル部分の刃先を特殊な形状にするのが難しく、研磨の度に時間がかかっていたのです。
そこで、「誰でも安定した品質でシンニング加工ができるドリル研磨機がどうしても欲しい!」と強く思うようになったのです。
購入機種:Huanyu 13A
今回購入したのは、3mmから13mmまでのドリルビットを研磨できる、本格的な卓上ドリル研磨機「Huanyu 13A」です。

「Huanyu(ファンユー)」というブランド名について調べてみると、どうやら特定のメーカーブランド名ではないようです。なお、製品としての評判は上々。
砥石ホイールには一般的なハイスドリル用の「CBN」と、超硬ドリル用の「SDN」がありますが、私の用途では当然CBNホイールを選択しました。
●CBNホイール:立方結晶窒化ホウ素でできた、ダイヤモンドに次ぐ硬さがあり、主にスチール系の研磨に適しています
●SDCホイール:金属被覆合成ダイヤモンドでできた砥石で、主に超硬などの非鉄の研磨に適しています
この機種を選んだ決め手

Amazonの商品紹介ページにあった、研磨後の美しい刃先とシンニング形状の写真に一目惚れしました。画像で確認できるその仕上がりが、まさに私が求めていた品質そのものでした。
市場には数千円から購入できる安価なドリル研磨機もありますが、プラスチック製で、いかにも「ちゃちい」作りのものがほとんど。仕事の現場でハードに使うには心もとないと感じていました。
もちろん、より高機能な機種も存在します。例えば、20mmまでの大径ドリルに対応したもの、シンニング量の調整機能付きのもの、ローソク型や一文字型といった様々な形状に研磨できる複合機などです。国内有名ブランドの「ホータス」製などは、安くても10万円を超えてきます。
私の用途では13mmまで対応できれば十分であり、性能と価格のバランスを考えた結果、この機種が最適だと判断。
ちなみに、今回は会社の経費ではなく、自分で使うための自腹購入です!運良くブラックフライデーセールで、通常価格62,800円のところを50,240円で購入できました。
<今回購入したドリル研磨機のスペック>
| 型番 | MR-13A |
|---|---|
| 研磨範囲 | φ3mm-φ13mm |
| 砥石 | CBN/SDC砥石(選択) |
| 砥石回転速度 | 4400rpm |
| 先端角 | 100°~135° |
| 電源 | 110V/60Hz |
| パワー | 120W |
| コレット | ф3、ф4、ф5、ф6、ф7、ф8、ф9、ф10、ф11、ф12、ф13計11個 |
| 包装寸法 | 32×18×19cm |
| 包装重量 | 8.7kg |
| 説明 | ◆小型で片手作業、精密で速い研削、操作簡単、スキルなしで簡単にプロ使用の仕上がりに出来ます。 ◆CBN砥石:HSS高速度鋼材のドリルの研磨に使用されます。 ◆SDC砥石:合金タングステン鋼材のドリルの研磨に使用されます。 ◆ドリルの先端角100°~135°(頂角)、逃げ角(後角)を研磨することができます。 ◆ツイストドリル研磨範囲:φ3mm-φ13mm、ドリルの外径によってスケールポインタを調整、一体式研磨、10秒でドリルを研磨できます。 ◆高硬度砥石:耐摩耗性と高靭性があり、砥石が摩耗し交換する必要がある場合は、付属のレンチで簡単に交換できます。 |
開封から実践レビューまで
開封の儀:ずっしりとした重さに期待が高まる
届いた段ボール箱は頑丈で、研磨機を持ち上げるとずっしりとした重量感があります。この重さがマシンの剛性の高さを物語っています。
付属品のコレット(ドリルを固定する部品)は、サイズごとに一つひとつ丁寧に小箱に収められており、欠品もありませんでした。梱包からも製品に対する配慮が感じられ、細部までしっかりした製品という印象です。

研磨の効果は?その切れ味に感動!
さて、肝心の研磨効果です。結論から言うと、「素晴らしい切れ味」の一言に尽きます。
切れ味が落ちていたドリル刃を研磨し、鉄板にあてがってみると、グッと食い込んでいきます。切子も両側から巻いて出てくるのでしっかり両刃で削れている証拠です。
正確なXシンニング加工のおかげで、下穴なしでの穴あけも格段にスムーズになりました。この綺麗な形状と精度は、手作業のグラインダー研磨では決して到達できなかったレベルです。

さらに、実際に使ってみて気づいた点や、購入を検討している方への注意点
1. 作動音と粉じん
研磨機なので、それなりに大きな音がします。工場内であれば周囲の音にかき消されて気になりませんが、ご家庭で使用する場合は、作業時間帯への配慮が必要です。また、金属を削るため粉じんも発生します。室内で使う際は、本体の下に新聞紙を敷くなどの対策をおすすめします。
2. 小径ドリルの研磨にはコツがいる
ドリル径5mm未満の細いドリルでは、研磨に偏りが出やすい傾向がありました。
【対策】 説明書通りの手順ではなく、片面ずつをほんの少しずつ、交互に研磨していくことで、バランス良く仕上げることができました。シンニングの際も同様に。
3. 交換用砥石は付属しない
海外の類似製品レビュー動画では交換用砥石が付属しているケースもあったため少し期待していましたが、この製品には付属していません。必要な場合は別途購入が必要です。(商品ページの梱包リストにも記載はなかったので、梱包ミスではないようです。)
4. 砥石の取り外しが非常に硬い
確認のために一度砥石ホイールを外そうとしたところ、信じられないくらい硬く締まっていました。六角レンチを使用してなんとか外れましたが、初回の交換時には、少し力が必要かもしれません。
5. 逃げ角の調整はできない
これは要望ですが、もし「逃げ角」まで調整できたら最高でした。この研磨機での仕上がりはおそらく逃げ角10°固定ですが、用途によっては7°くらいに調整(もっと刃を寝かせる)したい場面もあるのです。
ドリル研磨機の使い方(ステップバイステップ)
使い方 STEP1:準備
研磨作業を始める前に、本体の設置とドリルの下準備を済ませましょう。
1. 本体を設置する
ドリル研磨機本体を、平らで安定した場所に設置します。作業中に金属の粉じんが飛び散るため、汚れると困る場所であれば、下に新聞紙などを敷いておくと安心です。
2. 砥石の種類を確認する
本体に装着されている砥石が、研磨したいドリルの材質に適しているか確認します。
CBN砥石: 一般的なハイス鋼(HSS)ドリル用です。
SDC砥石: 超硬ドリル用です。
もし超硬ドリルを研磨する場合は、必ず別売のSDC(ダイヤモンド)砥石に交換してください。
3. ドリルを清掃する
研磨するドリルに付着している油や切り屑を、ウエス(布)などできれいに拭き取ります。
4. (任意)ドリルの予備成形
もし研磨するドリルの先端が大きく欠けていたり、折れたりしている場合、先にグラインダーやサンダーなどである程度形を整えておくことをお勧めします。このひと手間で、研磨機の砥石の消耗を抑えることができます。
使い方 STEP2:目盛りをドリル径に合わせる
次に、研磨するドリルの直径に合わせて、本体の「芯厚アジャスター」のダイヤルを調整します。
1. 基本的な合わせ方
まず、ダイヤルを一度右いっぱいに回し切ってから、左に戻しながら研磨したいドリルの直径に目盛りを合わせます。本体に貼られている「Web-Diameter」というラベルの矢印が指している位置が、設定値の基準となります。
例: 直径10mmのドリルを研磨する場合 → 目盛りを「10」に合わせる。
2. 特殊なドリルの場合
このダイヤル目盛りは、一般的なドリルの芯の厚さを基準に設計されています。しかし、ドリルの種類や状態によっては調整が必要です。
- ドリルが短くなっている / もともと芯が厚いドリルの場合
再研磨を繰り返して短くなったドリルや、もともと芯が厚く設計されているドリルの場合は、実際の直径より少し大きめの数値に目盛りを設定します。
(例: 10mmのドリルでも、目盛りを「12」に合わせるなど) - 深穴加工用など、特に芯が厚いドリルの場合
市販の高速回転用ドリルなど、芯厚が通常の約2倍ある特殊なドリルも存在します。この場合は、直径の数値を2倍した値に目盛りを合わせる必要があります。
例: 直径10mmの深穴用ドリルの場合 → 目盛りを「20」に合わせる。
補足: ダイヤルの目盛りは「13」までしかありませんが、2周目まで回せるように設計されています。14以上の数値を設定する場合は、目盛りを読みながら2周目まで回して調整してください。
【ポイント】
これらの設定はあくまで基本です。実際に使ってみて、切れ味が悪いと感じた場合は、目盛りの数値を少し大きくしたり小さくしたりして、最適な設定を探してみてください。
使い方 STEP3:ドリルのセット
1. 調整台でのセット
まず、これから使用するコレットとホルダーの穴に付着した研磨粉やホコリを、エアブローなどでしっかり取り除きます。
ゴミが残っていると、錆の原因になったり、ドリルを正確に固定できなくなったりするため、作業前には必ず確認しましょう。
ドリルの直径に合ったコレットを選び、コレットホルダーに「カチッ」とはまるように押し込みます。(コレットの溝とホルダー内部の突起を合わせる)

締め付けナットをホルダーに軽くねじ込んでおきます。
ドリルをコレットに差し込み、刃先が約5mm程度出る位置で、ナットを手で軽く締めます。この時点では、ドリルが少し動くくらいの強さでOKです。コレットのサイズとドリルのサイズの差によ りこのときの締め付け量は異なります。
仮組みしたホルダー一式を、本体の「調整台」に奥まで差し込みます。
ホルダーを右に回し、止まったところで固定します。これでホルダーの平らな面(カット面)が水平になります。
ドリルの先端を調整台の奥に突き当てながら、ドリル自体をゆっくり右に回します。すると、ドリルの刃が調整台内部の「ストッパー」に当たり、そこで止まります。

ドリルがストッパーに当たったその位置を動かさないように、締め付けナットをしっかりと締めて、ドリルを完全に固定します。
【注意】
締めすぎに注意! ナットを締める際、必要以上に強い力をかけると、内部のストッパーが破損する原因になります。
小径ドリルの場合: 2~4mm程度の細いドリルは、ストッパーで当たりがとりにくい場合があります。その際は、ドリルを軽い力でゆっくり回転させると、当たりを取りやすくなります。
2. 刃先の確認と、ドリル先端角度の調整
ドリルを調整台から引き抜き、ドリルの刃先とホルダーの平面部分が平行になっているか確認します。もし並行になっていない場合は芯厚アジャスターのダイヤル目盛の位置を変更するなどしてやり直してください。
ドリル先端角度を選んで調節し、六角レンチで締め付けます。

使い方 STEP4:研磨
いよいよ研磨作業です。研磨は「刃先の研磨」と「シンニング加工」の2段階で行います。
1. 刃先の研磨
本体の電源スイッチをONにします。
ドリルをセットしたホルダーを「刃先研磨ポート」にゆっくりと奥まで差し込みます。
ホルダーが左右に動かなくなるまで、ゆっくりと数回往復させます。研磨音がしなくなったら、片側の研磨は完了です。

ホルダーを一旦引き抜き、180度回転させて、再びポートに差し込みます。
手順3と同様に、研磨音がしなくなるまで左右に動かします。
【ポイント】
研磨中は、ドリルの柄(後端)には触れないようにしてください。センター軸がずれる原因になります。
5mm以下の小径ドリルを研磨する場合は、偏りを防ぐため、片面ずつ様子を見ながら少しずつ研磨するのがコツです。
2. シンニング加工
刃先の研磨が終わったら、その状態のまま、シンニング加工に移ります。
ホルダーを「シンニング加工ポート」へピンに合わせるようにゆっくり差し込みます。
こちらも刃先研磨と同様に、研磨音がしなくなるまで左右に動かします。

ホルダーを一旦引き抜き、180度回転させて、反対側も同じように研磨します。
両面の研磨音がなくなれば、すべての作業は完了です。
3. 作業完了
本体の電源スイッチをOFFにし、研磨したドリルをホルダーから取り外してください。見違えるように鋭くなった刃先が確認できるはずです。

メンテナンス方法
ドリル研磨機を長く使い続けるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。作業後は簡単な清掃を習慣づけましょう。
■ 作業前の安全確認
お手入れや部品交換を行う際は、必ず電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてから始めてください。
■ 本体・付属品のお手入れ
使用後は、本体や付属品に付着した金属の研磨粉を清掃します。
- 本体の清掃
調整台、刃先研磨ポート、シンニング加工ポート周辺に付着した研磨粉を、ハケやエアブローで取り除きます。その後、少量の油を染み込ませたウエス(布)で軽く拭き取ってください。
特に、コレットホルダーを差し込む穴の内部は念入りに清掃しましょう。 - コレット・ホルダーの清掃
使用したコレットとコレットホルダーも同様に、付着した研磨粉をハケやエアブローで取り除きます。
ホルダーのネジ部分やコレットをはめ込む部分は、油を染み込ませたウエスで軽く拭いておくと、錆び付きを防ぎ、スムーズな動きを保てます。
【注意】
油を直接スプレーしないでください。油と研磨粉が混ざって固まり、故障の原因になります。必ずウエスに染み込ませてから使用してください。
■ 砥石の交換方法
砥石が摩耗や目詰まりして切れ味が落ちてきたら、新しいものに交換します。(交換作業前には、必ず電源プラグを抜いてください)
付属の六角レンチを使い、本体裏側にあるネジを外して砥石カバーを開きます。
内部にある砥石の固定ネジを、同じく六角レンチで緩めます。
ファンと砥石を取り出し、新しい砥石と交換します。
ファンと新しい砥石をセットし、固定ネジをしっかりと締めます。
砥石カバーを閉じ、ネジで固定すれば交換完了です。
まとめ:ドリル研磨機 Huanyu 13Aは本当に“買い”か?
結論:プロなら“買い”。その理由は?
50,240円(セール価格)という初期投資は決して安くありません。しかし、仕事で毎日ドリルを使う方なら、間違いなく投資する価値があると断言します。
その理由は、以下の3点です。
- 作業時間の大幅な短縮
- 誰でも安定した高品質な仕上がり
- 特に面倒なシンニング加工の手軽さ
これまで手作業でドリルを研磨していた方なら、その時間と労力が削減され、仕上がりの品質が劇的に向上することに驚くはずです。
特に、こんな方には自信を持っておすすめします
- 仕事でドリルを頻繁に使うプロの方
- 面倒なシンニング加工を手軽に、かつ正確に行いたい方
- 精度の高い穴あけ作業が求められる現場で働く方
- ステンレスやチタンといった難削材の加工が多い方
一方で、こんな方にはオーバースペックかも?
- ドリルの使用頻度が低い方(年に数回程度)
- 趣味のDIYレベルでの使用を考えている方
- 特殊な研磨(一文字研ぎ、ローソク研ぎなど)をしたい方(専用機が必要です)
- 5mm未満の小径ドリルの研磨がメインの方
職人として使うなら、この「Huanyu 13A」は頼れる最高の相棒になります。
もし予算的に厳しい場合は、Amazonで3万円台から購入できる類似の卓上研磨機を検討するのも一つの手でしょう。
しかし、作業効率と仕上がり品質の向上を考えれば、この製品への投資は十分に元が取れると、私は自信を持っておすすめします。
おすすめ記事
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
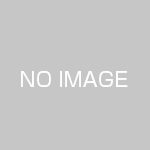



この記事へのコメントはありません。