ギロチンの刃が斜めになっている理由はなぜ?

ゲームや漫画、映画などで「ギロチン」という名前を聞いたり、その姿を見たことがあると思います。
重そうな刃が上から落ちてきて物を切断する… ちょっと怖いイメージもありますよね。ところで、そのギロチンの刃、よく見るとまっすぐではなく、斜めになっていることに気づいていましたか? 実は、それにはちゃんとした理由があるんです。
<結論>
ギロチンの刃が斜めになっている一番の理由は、「少ない力で、よりスムーズに物を切断するため」 です。刃を斜めにすることで、切る瞬間の力を一点に集中させ、まるで滑らせるように切り進めることができるのです。
メカニズムの説明:なぜ斜めだと効率的なの?
では、なぜ刃を斜めにすると、少ない力でスムーズに切れるのでしょうか? ここで、もし刃が地面と水平(まっすぐ)だったらどうなるかを想像しながら比べてみると、理由がよく分かります。
1. 力の集中度が違う!
もし刃がまっすぐだったら… 物を切る瞬間、刃全体が同時に物に「ドン!」と当たります。硬いものや厚いものを一気に断ち切ろうとすると、とてつもなく大きな力が必要になってしまうのです。
刃が斜めだと… 物が最初に刃に触れるのは、斜めになった先端の一点だけです。そこから刃が下に落ちるにつれて、刃が当たっている部分が徐々に横に広がっていきます。これは、ハサミで紙を切る時、刃が交差する一点から切り進んでいくのと同じです。押す力が常に刃と物が接している「狭い範囲」にギュッと集中するので、まっすぐな刃よりもずっと少ない力で切断できるのです。
2. 切り方が違う!
もし刃がまっすぐだったら… 基本的には、上から下に「押し切る」動きになります。粘り気のあるものや、繊維が強いものを切ろうとすると、きれいに切れずに潰れてしまったり、途中で引っかかってしまったりするかもしれません。
刃が斜めだと… 上から下に落ちる動きに加えて、刃が物に当たっている部分が横に「滑る」ような動きも加わります。これは、包丁でパンを切るときに、ナイフを前後に動かすのと同じような「切り裂く」効果(これを「せん断作用」といいます)を生み出します。この滑る動きがあることで、抵抗が少なくなり、よりスムーズに、そしてきれいに物を切り分けることができるのです。
関連:【QVC福島】「ギコギコはしません」の元ネタは?あの放送事故の真相を紹介
3. 衝撃と負担が違う!
もし刃がまっすぐだったら… 刃全体が同時に物に激突するため、切断時の衝撃が非常に大きくなります。これは、機械自体にも大きな負担をかけ、壊れやすくなる原因にもなります。
刃が斜めだと… 切断が一点から徐々に進むため、衝撃が分散されます。動作がよりスムーズになり、機械にかかる負担や騒音も大幅に減らすことができるのです。
<他の機械>
工場などで使われる大きな機械にも、同じ原理が使われています。例えば、「シャーリングマシン(MetalShredderMachine)」 という、鉄板などを切断する機械があります。この機械の刃も、ギロチンと同じように斜めになっています。斬首装置のギロチンは一気に落下させて切断する「落下式」でしたが、金属シャーリングは油圧や機械でゆっくりと上下動させて切断します。どちらも刃の角度で切り進める点は共通しています。硬くて厚い金属の板でも、効率よく、そして比較的きれいに切断することができるのです。これも、力を集中させて「せん断(切り裂く力)」を利用している良い例です。

<日常の道具にも応用>
実は、私たちの身の回りの切断道具にも、この「斜め」の原理が活かされています。例えば・・・
キッチンバサミ:料理用ハサミの刃をよく見ると、微妙に角度がついていることがあります。これも同じ原理で、切れ味を良くするための工夫です。
本の断裁機:図書館や印刷所で使われる本の裁断機も、刃が斜めにかかるようになっています。
ギロチンについて豆知識など
ここで、ギロチンそのものについて、いくつか豆知識を紹介しましょう。
歴史:ギロチンが処刑道具として有名になったのは、18世紀末のフランス革命の時代です。最初の公式使用は1792年4月25日、ニコラ・ジャック・ペルティエという強盗犯の処刑でした。
名前の由来:フランスの議会議員で医師でもあったジョゼフ・ギヨタンさんが、「もっと人道的な処刑方法を」と提案したことから、彼の名前をとって「ギヨタン(Guillotin)」と呼ばれ、それが変化して「ギロチン(Guillotine)」となりました。実際の設計は外科医のアントワーヌ・ルイが担当し、最初は「ルイゼット」と呼ばれることもありました。
処刑方法:それまでの処刑方法(例えば、斧や剣で首を切り落とすなど)は、執行する人の腕によっては一度で成功せず、罪人に多くの苦痛を与えることがありました。ギロチンは、機械的に素早く確実に首を切断することで、苦痛を最小限に抑える(と考えられた)人道的な目的で導入されたのです。
提案者ギヨタン医師:実はギヨタン医師自身は死刑制度に反対していました。ただ、死刑が避けられないのであれば、せめて苦痛の少ない方法にすべきだと考え、この装置の導入を提案したと言われています。彼自身はギロチンで処刑されていません。皮肉なことに、彼の名前が恐怖の象徴として残ることを、生前のギヨタン医師は大変悩んでいたそうです。
意識は残る? まばたきの話:「ギロチンで首を切断された後も、数秒間は意識があり、まばたきをした」というような話が伝わっています。有名なのは、フランス革命期の科学者ラボアジエの弟子が、切断後にまばたきをするよう師匠に頼んだという逸話ですが、科学的な根拠ははっきりしていません。現在では、脳への血流が瞬時に途絶えるため、意識はほぼ即座に失われると考えられています。
フランス最後の使用:フランスでは1977年9月10日に最後のギロチン処刑が行われ、1981年に死刑制度そのものが廃止されました。最後に処刑されたのはハミダ・ジャンドゥビという殺人犯でした。
子供のころのトラウマ:時のオカリナの闇の神殿
ギロチンと聞いて、私が個人的に思い出すのは、子供の頃に夢中になったNINTENDO64の「ゼルダの伝説 時のオカリナ」というゲームです。「闇の神殿」というダンジョンが登場するのですが、闇の神殿には、通路のトラップとしてギロチンが仕掛けられていて、通過するタイミングを間違えるとダメージを受けてしまいます。
子供心にそれが本当に怖くて、ドキドキしながらコントローラーを握りしめていたのを覚えています。
というか「闇の神殿と井戸の底」は当時多くの子供たちがトラウマになったのでは?
ゲームの中のギロチンの刃も、やっぱり斜めですね。皆さんも、ゲームや映画でギロチンを見かけたら、刃の形に注目してみると面白いかもしれません。

ポップカルチャーでのギロチン
ギロチンは歴史的な処刑道具ですが、現代のポップカルチャーにも様々な形で登場します。
映画: 「レ・ミゼラブル」や「マリー・アントワネット」などの歴史映画では、フランス革命の象徴として登場します。
ホラーゲーム: 「バイオハザード」シリーズや「サイレントヒル」などでは、恐怖を演出する罠として使われることがあります。
アトラクション: お化け屋敷やハロウィンイベントでは、ギロチンの模型が展示されることもあります。
こうした表現を通じて、ギロチンは「恐怖」や「革命」の象徴として、現代文化にも根付いていると言えるでしょう。
まとめ
ギロチンの刃が斜めになっているのは、単なるデザインではなく、「力を一点に集中させて効率よく切る」「滑らせる動きでスムーズに切る」「衝撃を和らげる」 といった、力学に基づいた合理的な理由があるからでした。
この仕組みは、包丁やハサミといった身近な道具から、工場で使われる大きな機械まで、様々な場所で応用されています。
ちょっと怖いイメージのあるギロチンですが、その形に隠された科学的な工夫を知ると、また違った見方ができるのではないでしょうか。身の回りの道具や機械にも、なぜそのような形をしているのか?と考えてみると、面白い発見があるかもしれませんね。
おすすめ記事
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
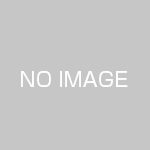


この記事へのコメントはありません。