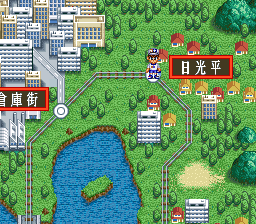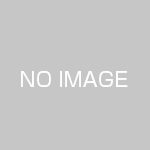FRAGILE ~さよなら月の廃墟~ 記憶アイテムまとめ(クロシェット)
こちらはクロシェットアイテムの記憶になります。長いので別記事にしました。その他の記憶アイテムはこちら
目次
【七色クロシェット】
息絶えてしまった、たくさんの彼女達を見た。
死の床、という言葉を思い出した。白く明るい路地裏で、彼女達は息絶えていた。その理由について、詮索しようとは思わなかった。
死は覆らない。死は戻らない。死はただそこにあり、何処へにも行かない。
どうして、と涙が落ちたのは、私があまりにみすぼらしい身体をしていたからだ。愛された覚えも無いのが、一目で見て分かる様な姿だったから。
この街では、家族に迎えられたその日に、家族独自のクロシェットが与えられる。それは愛された証。家族の証拠。
私は生まれてからただの一度も、己のクロシェットを持たなかった。
なのにこうして私は生きて、家族から惜しみない。愛を与えられていた筈の彼女達は無残に死んだ。毒かもしれなかったし、病かもしれなかった。或いは直に私も、死の風に吹かれてしまうのかもしれなかった。
でも今、私は生きている。ざまを見なさい、と心の中で一つ悪態をついた。ねぇほら、ごらん。貴女達が嗤った私はこうして生きて、私を蔑んだ貴女達は死という罰を受けたのよ。ごらん!私は生きている!
そう叫んでも、誰の瞳も開かれる事は無く、私の涙も、止まる事は無かった。
一つ、また一つ、地に落ちたクロシェットを拾いながら、私は決して彼女達の死を悼まない事に決めた。
地を這う様に生きてきた私ならば、貴女達の死も、生も、愚弄するだけの資格がある筈だった。私の物でないクロシェットの音だけが、弔いの鐘の様に、虚しく空に帰って行った。
【赤いクロシェットのアンリ】
コン、ココン、コン。
小さな家に嵌った小さな窓の奥からは、白木を弾く様な、咳の音がする。部屋の中には小さなベッドがあり、小さな人間の子供の身体が横たわっている。
『ぼうや、さあもう眠らないといけませんよ。』
そう言いながら部屋に入って来たのは、背の高い女性だった。ぼうやの背中をさすりながら、ランプの炎を消しに来た様だった。
『嫌だ。』
とぼうやは首を振る。
『嫌だよ。アンリが帰って来るかもしれない。』
『ぼうや……。』
母親は困り顔だった。彼女には何らかの予感があり、分かっているのだ。ぼうやが帰りを待っている「アンリ」がもう戻って来ないという事を。
『アンリは絶対に帰って来るよ。今までだって帰って来たもん。僕が赤いクロシェットをあげた、僕の妹だもん。』
そう、確かに、アンリはぼうやの妹だったのだろう。私は窓の外から二人を眺めながら、ぼうやの事を思い、病気がちな可愛いぼうやよりもまだ小さかったアンリの事を思い出した。
かつて彼女がぼうやの元を訪れた時、ぼうやがどれほど喜び、どれほど愛おしみながら赤いクロシェットを手渡したのか。見てはいない私も、目の前にその光景を思い浮かべる事が出来た。
『アンリが帰って来たら、起こしてあげるから……。』
『アンリのクロシェットの音は、僕が一番分かるんだよ!』
アンリのクロシェットは、赤い小さなものだった。アンリはもうこの世におらず、ただ赤いクロシェットだけが、彼女の死体から奪い盗られてここにある。
月を仰ぎ、夜空を望んで、死者の冒涜、という言葉を考えた。私が今から行う事は、死した彼女達に後ろ足で砂を掛ける事そのものだと思った。事実まさにそうして、彼女達の死体を見捨てたのに、その上でまだ、罪に罪を重ねる様に。
一方で、これは復讐である、と思った。これは正当な復讐である。みすぼらしい娘だと私を嗤った彼女達への、復讐である。か細い声で、ぼうやを呼ぶ。
クロシェットを鳴らす。ぼうやが一番分かると言う、彼の妹である印。窓が開く。アンリ、とぼうやの声が私を呼ぶ。ええそうよ、ええそう、私。私がアンリよ!
ぼうやの腕が伸び、私を抱きしめる。どうしてこんなにぼろぼろになったのかと言いながら。ぼうやの知る美しい少女と比べればもう、変わり果てた姿、変わり果てた声。でも、赤いクロシェットだけは、変わらないから。私の復讐は、確かに成ったのだ。
私はアンリ。赤いクロシェットのアンリ。小さなぼうやの腕に抱かれる、小さな末娘。
【青いクロシェットのフルール】
全く最近の親方は敵わんね、と工場の裏で話している若い人間の声がする。所々に黒ずんだ、揃いの白い服を着て、苦い顔をして口元から紫の煙を出している。
私は二人の人影の側までそろそろと歩み寄り、柱の裏から聞き耳を立てる。
『また納期が遅れているぜ。』
『俺は昨日も親方に殴られたよ。灰皿がいっぱいだからってさ。』
『そんな事言われたってなあ、親方の仕事が終わらなきゃ。』
『煙草を喫む位しか、俺等の仕事は無いってもんだ。』
『敵わんなぁ。』
『あぁ全く敵わんね。』
トンカン木槌を叩く音がする。この工場は、腕の良いけれど偏屈な、親方が一代で築いた工場だそうだ。今では二人の若手も抱えて、ひがな一日家具を作っているという。けれど二人は若い手を合わせて四本も遊ばせて、白く煙った溜め息ばかりをついている。
『やっぱり、あれかね。』
『あれ位しか無いだろうねぇ。』
『聞いてみるか?』
『馬鹿、今度は横っ面じゃ済まなくなるぜ。生きてやすりに掛けられても文句は言えねぇよ。』
『あーあ。敵わんなぁ。』
『全く敵わんね。』
そうして二人は、また白い溜め息。
『フルールが姿を見せなくなってもう一ヶ月かぁ。戻って来ないのかねぇ。あの器量よし、ついに乱暴な親方に愛想を尽かしちまったのか……フルールがちょちょいと顔を見せてくれりゃ、親方の機嫌なんて、一変で直っちゃうのになぁ。』
私が盗み聞いたのはそこまでで、するりと身体を反転させて、工場の壁に沿って歩いた。私が今首から下げる、青いクロシェットはこの工場の印だった。
今日はだから、私は親方のフルールになりに来た。工場の窓辺まで行くと、奥から酷い大声がした。
『だから言っただろう!出来ねぇもんは出来ねぇよ!お前の言い分なんか知るかい、糞くらえ!』
受話器を投げる音に、木片が散らばる音が重なった。私は耳の先まで驚いて、ふるふるふるっと身体を震わせる。生きてやすりに掛けられる、という言葉が頭の中を回っていた。
それは、きっと、とても、痛い。青いクロシェットを見下ろして思う。死ぬより、痛い?どちらも体験した事が無いから分からないけれど、多分、死ぬ方が痛いのだろう。
そう考えたら、震えが止まった。フルールはきっと、もっと痛かった。
『やってられるか!』
今度は窓から出来損ないの家具が投げ捨てられた。やっぱり怖かった。
おののき過ぎた性でリン、と青いクロシェットが鳴り響く。親方は茶色く皺がたくさん刻まれた顔で私を睨みつけた。
濁った灰色の目に、見破られてしまうんじゃないかと思った。私は、フルールの様に美しい姿をしていなかった。お前は俺の愛したフルールではないと、生きたままやすりで削られてしまうのかもしれない。
ぬっと手の平が伸びて来た。マメばかりで木の皮の様にささくれだった手の平だった。殴られる、と思ったけれど、その手は、私の頭を包む様に乗せられた。決して強くなり過ぎない手で、私の頭を撫でて。
『こんな、痩せて。』
潰れた声は、かすれて呻き声の様だった。涙声が私の心まで震わせた。疑わないのか。見破らないのか。私はこうして、頭を撫でられても良いのだろうか。私が何も言えないでいると、親方の腕が軽々と私を抱き上げ、『お前等!』と工場の裏に叫んだ。
『何いつまでもシケってやがんだ!頭から漆を被りたくなけりゃ、新しい材木を磨け!取り掛かるぞ!』
怒鳴られた二人は、けれど目を輝かせて。
『親方のフルールが帰って来た!』
と諸手を挙げる。何も言えない私の代わりに、青いクロシェットが軽やかに鳴る。だから私は、ここでの名前を手に入れた。
私はフルール。青いクロシェットのフルール。意固地な親方に撫でられる、家具職人の愛娘。
【紫のクロシェットのシルビア】
明け方よりもまだ早く、ようやく夜空に微かな光がにじむ頃。私は気だるく騒ぐ夜の街を歩いていた。
喧噪は耳に痛い。大通りからは怒鳴り声がして、路地裏からは嬌声がする。
ごみだめを避けて歩く。こうして淀んだ場所にいると、これまでの自分の暮らしを思い出してしまう。
扉が半開きになった店があった。中からは多分、流行りではない音楽が流れていて、店の入り口の看板も、右半分が暗かった。
その看板には「silvia」の文字。
『ねぇママ、そろそろお止めになったらぁ。』
甘い声がカウンターの向こうから聞こえる。カウンターの端、壁に半身をもたれる様にして肩を露出するドレスを着た、髪の長い女の人が座っていた。
『ママのする事は勝手だけどぅ。流石に最近飲み過ぎだと思うわぁ。』
甘い声はまだ若く、猫の雄が雌を呼ぶ様に間延びしていた。
『身体に障るとおも―――』
『リカ』
遮る様にグラスのコップがカウンターを叩く音は、無骨で重たかった。沈黙が降りる。
『もうぅ……知らないんだから……。』
グラスの中身を変える為に、カウンターの女性がそれを引き上げ、けれど悪あがきの様にぼやいた。
『ママの身体を想って言ってあげてるのぉよう。最近全然肌のハリも無くってさ、そんなんじゃ先代のママも何て言うか……。』
『リカ』
同じ重たい調子でもう一度。今度は煙草に火をつける音と一緒に。
『それ作ったら、もう上がりな。』
『えぇー。』
『二度と来るなって言われたいのかい!』
叫び声は突然だった。けれどリカという女性は軽く肩を竦めただけで、手を休めはしない。
『やぁよう。だって、ママに捨てられちゃったら、さっみしーもん。』
コツン、と置かれたのは、鼻に匂いのつく酒ではなく、白い液体。
『先代のママも、お酒で突然倒れちゃったじゃあん。ママがそうなったらやだもーん。お疲れさまー。』
高いヒールが近付いて来る音がして、慌てて看板の裏に隠れる。
『あれ?』
きょろきょろと明け方の路地裏でリカが首を回す。
『シルヴィアちゃん……?』
呼ばれた名前が、誰の事かは、私にはもう分かっている。
はぁ、とそこで初めてリカが疲れた溜め息を漏らして、汚れた道を、足を放り出す様に歩いて行く。その背中が見えなくなって、ようやく心を決めた。
死したシルヴィアがどんな生い立ちであったのか、私は直接聞いた事が無い。けれどとても寡黙で、媚びた所が無くて。彼女だけは、嫌いではなかった。
けれど私は彼女の名を騙る。復讐であると最初に思った。これは確かに復讐だった。私よりも幸福な生き方をして来た彼女達の。そして私自身の、手酷い運命への報復だった。
1歩、もう1歩、そろそろと半開きのドアから店内に入り、ママ、と、か細い声でささやいた。
リカが消えたと同時にカウンターにつっぷしたその人は、緩慢な仕草で半身を持ち上げ、空耳でも聞いたかの様に恐る恐る、振り返った。
もう一度ささやく。ママ。すると彼女は化粧の落ちた、シミの目立つ顔を歪めて。
『なぁに、アンタ……。』
泣きそうな声で笑った。
『アンタ、また、そんな、ウチに初めて来た時みたいじゃないのよう。』
その言い方は、ほんの少し、先のリカという女の人に似ていた。
『何よ、ちょっと姿見せなくなったと思ったら、アンタもう何をしてたのよ。ほら、飲みなよ。アンタにあげるわよ。何でもあげるわよ。もう、もう……。』
良かった……と、滲む様な声で、私にグラスを差し出した。もしかしたらシルヴィアも、ここに来て初めての日に、こうして暖かなミルクを貰ったかもしれなかった。
ごめんねと、初めて一度、心の中で呟いた。
私はシルヴィア。紫のクロシェットのシルヴィア。夜の街でママに抱かれる、ママの為の少女。
【黄色いクロシェットのロッテ】
花壇に水を撒く背の高い人間。白いシャツと黒いズボンが質素で清潔だった。
『先生。』
声を掛けたのは、小さい子供が二人。水を撒く男を見上げていた。
『うん?どうしたのかな。』
先生と呼ばれた男は慣れた仕草で屈み、掛けていた眼鏡の奥から男の子と目を合わせた。
『せんせい、ねえ、ロッテは?』
言ったのは女の子だ。言われた「先生」の顔が曇ったのが、遠目にも分かった。
『先生。ロッテは、もう戻って来ないの?』
追従する様に男の子も良い、『うーん……。』と、先生は眉を下げた。
その内、周囲に同年代の子供が集まって来た。どの子供も一様に白いシャツが、遊びでくたびれていた。
かつては「ロッテ」も、黄色いクロシェットを付けて、この輪の中にいたのだろうと私は想像する。小さな子供達には親がいない様だった。先生と呼ぶ青年と共に、大きく質素な家に暮らしている。
『どうしたんだろうね。これまでも、時々いなくなる事はあったけど……。』
静かな口調で先生が言うと、子供達は口を開いた。
『またロッテと遊びたいよ。』
『ロッテ、病気になってないかな。』
『怪我とか。』
『さみしくないかなぁ。』
『絶対さみしいって。』
不安を広げる子供達に、先生が問うた。
『君達は、ロッテが寂しがってると、悲しいかな?』
『悲しい。』
『いやだぁ。』
と声が上がる。先生は頷き―――
『それならロッテもきっと、君達が淋しがっていると知ったら悲しむよ。ね?』
と優しく言った。私はその様子を遠目で眺めながら、しばし迷った。ロッテの黄色いクロシェットが、この孤児院のものだと分かっていたからここまで来れたけれど、彼女はこの施設の家族ではないのだろうか。姿を消しても構わないのか。
先生に宥められ、めいめいに自分の遊び場に戻る子供達。けれどそこに、そばかすのある巻き毛の少女が一人残っていた。
『でも、あたし達は。』
その少女は自分の足元を見ながら、小さく呟く。
『ロッテが、寂しがってないとしても、悲しいわ。』
少女の頭上に先生は手のひらを乗せた。
『仕方の無い事だって、あるのかもしれないね。』
『あたし知ってるんだから!』
強い視線を上げて、少女が言う。
『仕方が無いなら、先生が毎晩毎晩、あたし達が寝た後に、ロッテを探しに行ったりしていないもの!』
しぃっと、その口元に先生が指を当てる。
『みんなが心配するだろう?』
『あたしだって、先生を心配しているのよ!』
ませた言い方に、『うん』と困り顔で先生は頷く。
『知ってる。ごめんね。』
そうして先生は水やりを持ったままで、宙を見ながら静かに言うのだ。
『僕は、さほどロッテの事を心配してる訳じゃないんだ。きっとロッテはここを出て行っても生きていける。ただ、みんなはさ、ロッテを家族と言ったじゃないか。僕はその言葉を大切にしたいと思うんだ。家族らしくない僕らだからね、家族って言葉を人よりもう少し大切に出来たら良いなって思うんだよ。』
夜になり、孤児院の灯りが消えて暫くして。孤児院から抜け出した影の前に私は静かに現れる。一瞬、先生は私の姿を見て歩みを止めた。
月夜の灯りの下でさえ、私はやはり変わり果てた姿だろう。この音だけが頼りである様に、私はクロシェットを鳴らした。
『……ロッテ、なのかい?』
ええそう。私が、ロッテよ。
『帰って来てくれるのか。僕らの『家』に。』
勿論こんな私でも良かったら。
戻った孤児院では、先生の不在に泣く子供達をそばかすの少女が懸命に宥めていた。これまで何日も、先生に隠れ、子供達の夜を守って来た様だった。
そんな少女を抱き寄せて、先生は私の帰還を全ての子供達に、全ての家族に告げた。
私はロッテ。黄色いクロシェットのロッテ。たくさんの家族を持つ、優しい孤児院の家族の一人。
【橙のクロシェットのビスク】
あの家に住む「センセイ」は奇人だよと、街の人々はみんな言ってる。その家は歴史のありそうな古い造りだったけれど、手入れが全く行き届いておらず、ぼろ家と言っても差し支えがない程だった。
鍵の掛からない扉は、鍵を掛けていないのではなく、鍵自体が存在していない。盗人を歓迎しているのかと思わせる様な素振りだが、中に1歩踏み込めば、物を盗む気も無くなる位の荒れ様だった。
家をそのまま家人に照らせば、それは正しき奇人と呼ばれるに値するだろう。その奇人のセンセイは、廊下に倒れていた。
死んでいるのかと思ったけれど、時折指先が痙攣する様に震える。眠ってさえもいない様だった。
老人の様に骨の浮いた手の甲だったが、髪のつやだけは若く見えた。黒い髪に、倒れる時までも絶えず黒い縁の眼鏡を掛けていた。きっと長い間眼鏡を掛け過ぎて、身体の一部になってしまったのだろう。
倒れている。ごみの様な布の様な家具の様なものを掻き分けて、私が家に入った事も分かっていない様だった。
『ビぃすクー。』
時折私を呼ぶ頓狂な声が聞こえる。呼ばれる度に驚いて、身体を震わせると同時にクロシェットも震える。
涼やかな音。その音だけは耳に入る様で、飛び上がる様に身体を起こして私に背を向けたまま。
『近寄るな。』
そんな酷い事を言うのだ。
『絶対来るなよ。』
そう言いながら、机の様な、机であったものの様な、紙の散乱するそこに戻る。がりがりと頭を掻きながら、腕を動かし続けるのだ。直に何やら奇声を上げては、また地に倒れ、その繰り返し。
私はただひたすらに呆然と、センセイの部屋の隅に佇んで、夕暮れ家を後にするのだった。クロシェットの音は軽やかに鳴る。けれど、首を傾けずにはいられない。
あの人は本当に、ビスクの家族なのだろうか。
数日空けて様子を見に行く様になって何度目か、何時も見ても同じ様に奇妙な行動しか取らない奇人が、床に倒れる事も無く、ただ一心不乱に紙束に向かっていた。鬼気迫る背に気圧されて、クロシェットが鳴らない様に気を遣う。
そのまま部屋の隅に佇んでいると、その内ざっとペンの滑る音がして。
『ふー……。』
大きな溜め息。そして大きな伸びを一つ。結局彼はそのまま後ろへと倒れた。
『あがりだぁ……。』
空気の抜けた様な声は、何時もの棘のあるものとは全く違ったものだから。私はやはり首を傾け、同じ様にクロシェットが涼やかに彼を呼ぶ。彼は倒れたままで、呻き声を上げる。
『ビスク。ビスク嬢ー。』
今日もまた近寄るなと言われるのかと思えば、亡霊の様な動きで細い腕が上がり、手招きをされた。
恐る恐るという様に歩み寄り、覗き込むと、突然首根を掴まれ、私もセンセイの上に倒れ込んだ。驚いて固まっていると、彼の心臓の音がする。彼は緩やかに目を閉じて私を撫ぜた。
『……何だ。ビスク、お前。ちょっと見ない間に……痩せたなぁ。』
骨の浮いた手は少し乱暴だが、優しい仕草だった。答える事が出来ずにいると、心臓の音が少しずつ柔らかくなっていって。まどろみの言葉が私に降り注ぐ。
『……くっそ……ようやく、寝られる……。』
言葉の終わりはもう夢の中の様で、そのまま寝息に変わっていた。けれど私を抱く手だけは変わらず、ああそうか、と疑問が解ける様な思いだった。
ああそうか、オレンジのビスクはきっと、この為の、家族なのだ。そうして私も自身の心臓の音を溶かす様にそっと、静かに目を閉じた。
私はビスク。橙のクロシェットのビスク。奇人と呼ばれる文筆家に、安らぎの眠りを与える、センセイの養い娘。
【銀のクロシェットのクリス】
銀のクロシェットは特別目立つ装飾が無く、けれどとびきり美しい音で鳴った。
こんな素敵なクロシェットは一体どの様な家のものなのだろうかと思っていたら、見た事も無い様な大きなお屋敷に住む、他に家族のない老婆のものだった。
『奥様、お食事の時間です。』
『ありがとう。』
『奥様、庭のユリが咲きました。こちらの花瓶に。』
『なんて良い香り。』
『奥様、雨が降ってきました。窓を閉めさせて頂きます。』
『そうね。カーテンも、よろしくね。』
たくさんの使用人を抱えていた彼女は、身の回りの事を使用人に任せながら、安楽椅子に座り、何時も静かに音楽に耳を傾けている。
レコードを変えるのでさえ、使用人を呼ぶ始末であったが、多くの使用人は女主人である老婆を慕っている様だった。
そして老婆は日に何度か、使用人にこんな事を言うのだ。
『ねぇ、クリスを呼んで来てくれる?』
或いは。
『クリスはどこ?』
またある時は。
『クリスを探して頂戴。』
老婆に粛々と従う使用人達も、この要望には苦い顔をした。
『奥様、クリス様は……。』
使用人が控えめにそう言うと、『ああ、そうでした。』と老婆は言葉を皆まで言わせない。
『あの子はもういないのよね。そうだった、そうだったわ……。』
呟きながらしっかり頷くのに、半日も経たない内に、彼女はまた言うのだ。気に入りのレコードを止めさせて。
『私の可愛いクリスは一体何処に?』
ある雨の日の夕暮れ、お屋敷が騒がしかった。
『奥様。』
『奥様……!』
ぱたぱたと歩き回る、屋敷の使用人達。やがて1人の使用人が、絶望的な声を上げた。
『どうして、奥様の杖が見当たらないわ!』
外はさほどに寒くはなかったが、霧の様な雨が絶え間なく降り続いていた。
『まさか、お一人で外に。』
さあっと青ざめた彼等彼女等は、めいめいに動き始めた。外套を纏い、或いは外へ連絡をして。私も彼女達の様子から目を逸らし、雨の街を駆け出した。
雨を駆けながら、何処かで百合の甘い香りを嗅いだ気がした。屋敷から随分離れた公園の裏通り、見えた人影が屋敷の老婆だと、何故か遠目にもすぐに分かった。
数人の影に囲まれ、しきりに話し掛けられている。
『ほら、そんなんじゃ風邪を引くだろうよ。交番に行かないかい?』
老婆の靴は柔らかな内履きで、仕立ての良い服も雨に濡れていた。男性が老婆の手を引こうとするが、老婆は虚ろに俯いて、断固としてそこを動かない様だった。
痺れを切らした男達が老婆を置いてその場を離れる。私は老婆の世界に入る場所まで行き、声を掛ける事はせずに、銀のクロシェットを鳴らした。
雨の中に、澄んだ音。はっと顔を上げた老婆は、私を見て、濁った瞳を細め、かすれた声を上げた。
『クリス……?』
頷く様にクロシェットを鳴らし、身体を反転させる。
『待って、クリス、クリス……!』
追って来る声と、杖の音。私では彼女を屋敷まで運べないだろう。せめて、使用人のもとまで。何度も振り返り、足を止め。老婆が私を見失わない様に、美しいクロシェットの音を灯台にした。
やがて屋敷の使用人の1人が、老婆を見つけ、『奥様……!』と駆け寄って来るに至り、ようやく私は、その濡れた身体を老婆に抱き締められた。
いなくなった筈のクリスが、こんなに変わり果てた姿で戻って来た事に、使用人達は驚きを隠せない様子だったが、誰も私をクリスではないとは言わなかった。
老婆が私をクリスと呼んだのだから、彼女達はまた粛々とそれに倣い、皆愛する女主人の無事と喜びを祝ったのだった。
私はクリス。銀のクロシェットのクリス。大きなお屋敷を持つおばあさまの小さな小さな、可愛いクリス。
【桃のクロシェットのマリア1】
私が手に入れたもの。暖かな手と、たくさんの名前。
月曜日のアンリ。火曜日のフルール。水曜日のシルヴィア。木曜日のロッテ。金曜日のビスク。土曜日のクリス。
そして一日だけは、私は何者でもない「私」になる。
復讐のつもりだった。私よりも幸福であり、私よりも先に死んだ彼女達へ。弔いも冒涜も等しく終わり、嘘の私だけがここに残る。
何時からか私は未来に想いを馳せる様になった。何時か、ねえ何時か。何時か私は恋をしよう。
愛おしい誰かを見つけたら、私は初めてその人から名前を貰うのだ。誰の代わりでもない私だけの愛の名を。そう心に決めていた。
なのに、私はどうして。私はどうして、出会ってしまったのだろう。
彼は街を見下ろせる切り立った崖に佇んでいた。美しい横顔だと思い、美しい立ち姿だと思った。けれどその美しさだけが足を止めた理由ではなかった。
理由など要らなかった。私はその日、どのクロシェットも付けておらず。それゆえ、決して何者でもなかった。
彼の足元に落ちた淡い二連の桃色のクロシェット。彼の物ではない。ただ彼の愛情だけが、残滓としてそこにあった。その横顔は絶望を知っている。そこに浮かぶのは死に至る空虚である。どれほど見つめても、声を上げても、私を振り返る事は無いのだろう。
私は薄桃色のクロシェットを拾い上げる。その涼やかな音色だけが彼の耳に届き、彼の心を動かし、彼の目を覚まさせるだろう。それからかすれた声で、信じられないという表情で、貴方は言うのだろう。かつて愛した「彼女」の名前を。
『……マリア?』
そうして私は、泣き出してしまいたい気持ちで微笑んで、彼に言うのだ。
――そう、私がマリアよ。だから、「私」はこの世の、何処にもいない。
『君の本当の名前を教えて欲しい。』
私は軽やかに笑い声を上げて答える。
マリアよ。
彼は困った顔をして、私に寄り添うだろう。
『それは、君の名前じゃあない。』
でも、貴方の愛した名前でしょう?私は彼を愛していた。けれど彼が愛していたのは私ではなかった。
この桃色のクロシェットの本当の持ち主。死しても消える事なき恋敵。本当に彼に愛されたのは彼女だけ。私は彼女を恨み、憎み、その名と存在を奪った。それがどれだけ自分を惨めにさせるとしても。
『もしも君に出会っていなかったら。あのまま僕は朽ちていたと思う。』
その言葉だけが私の救いになるのだろう。貴方が幸せならば、私の名など、永遠にいらない。
嵐がやって来る。明け方から窓を叩き始めた強風は見る見る内に暗雲を呼び、森の木々を横殴りにしていた。私はおばあさまの温かい毛布から抜け出し、夜の街を抜け、山小屋へと向かう。
かつての私の隠れ家。クロシェットを取りにそこへ戻る度過去を思い出す。今はたくさんの名で呼ばれる私。じゃあこの山小屋に、残った亡霊は一体誰?
一際大きな雷光が、雷鳴と同時に走った。爪の先まで逆立つ気持ち。木々の折れる音。悪寒が走り、駆ける速度を思わず速めた。背中から這い上がる震え。小屋に近付くにつれ、私は最悪の事態を知る。
大量の煙。強い臭い。肌をじりじりと焼く、灼熱。山が、燃えていた。強風に煽られ火はみるみる広がっていく。私は衝動のまま小屋に転げ入る。
地獄の様な熱を感じる。けれど、どうかクロシェットだけは。彼女達の生きた証。そして私の生きる場所。七つのクロシェットを掻き集め、外へと逃げようとするが、小屋の入り口はもう火が回っていた。
割れた窓のガラスに飛び乗る。生きたまま焼かれる苦しみ。あちこちから崩壊の音がする。窓の外は切り立った崖だった。私は転がり落ちる様にして飛び降りる。
七つのクロシェットを、強くその歯に噛み締めて。
【桃のクロシェットのマリア2】
闇に落ちた私の意識を戻したのは、頬を叩く雨の滴だった。
まだ山火事の強い臭いはしたが、降り出した雨は雨脚を強めていく気配だった。
助かった、とは思えなかった。山の地に身体を伏せて、両手両足の感覚がもう感じられなくなっていく。
これは罰かと宙に問うた。死した彼女達の幸福を自分のものにした、浅ましい私への罰なのだろうか。
『……!』
灰色の視界の中で、私を呼ぶ声がする。いいえその名は私のものではない。けれど。けれど。
『……ア!マリア!』
呼ぶ声は確かに、私の愛した貴方のもの。
『マリア、しっかりしろ、死ぬなマリア……!』
ああ、貴方。愛おしい貴方。絶望はしないで、とささやきを絞り私は言う。絶望はしないで。どうか、お願い。
――生きて。
私を失えば、彼は生涯で二度、愛したマリアを失うのだと思った。彼だけではなかった。
アンリ。フルール。シルヴィア。ロッテ。ビスク。クリス。
美しい彼女達。殺さないで、とかすれた声を上げた。愛された彼女達をどうか殺さないで。
私は震えながら、七つのクロシェットを彼に託す。もしも出来るなら、貴方が私に代わって。どうか、あの全ての愛しい家族に絶望だけは。
彼は何か言いたげに私を見た。そしてクロシェットを受け取ると、踵を返して走り出す。
遠ざかり小さくなるその背が、雨と涙で揺れ、かすんだ。名を呼ぼうとした。もう声は出なかった。声が出ていたら言ってしまったかもしれない。
――行かないで。
冷たい雨が、山の熱と共に私の命をも奪うのだろうと思いながら、最後に私は家族と愛する貴方の事を考えた。
愛されたのは私ではなかった。けれど私は確かに、あの温かな優しい手を愛したのだった。嘘をつき、死者を冒涜し、復讐を果たす為に。
なのに今、涙が落ちる。死の間際で彼女達と一番近い場所まで来て、ようやく本当に彼女達の為の涙が落ちたのだった。だって。だって、そうでしょう。そうでしょう、みんな。
……生きていたかった、ねぇ?
雨は山を灰色に濡らし、視界からは光が潰えた。闇の中、雨に紛れて。
クロシェットの澄んだ音がした気がした。自身の耳がまだ動いたのが分かった。神経を研ぎ澄まし、その音を探した。そしてその音を追う様に複数の足音と、声。
『………アンリ!』
その声は、幻だと思った。クロシェットの中に封じ込められた、淡い思い出なのだと思った。だって、呼ばれる訳が。
『フルール!』
『シルヴィアぁ!』
嘘、と私のまぶたが震える。
……どうして……?
灰色の世界の向こうに、たくさんの人影。雨の中、私を取り囲んで。ぼうや。親方。ママ……。
『ロッテ!』
『ビスク……っ!』
『クリス!』
嘘よ。子供達。センセイも。おばあさま……!
だめだ、と私は声にならない声を上げた。だめ、私を見ないで。嘘を見破らないで。糾弾しないで。私は、貴方達の愛した少女ではないのに……!
『知っていたよ。』
声がした。私の為に、七つのクロシェットを使い家族を呼び集めてくれた貴方。温かなタオルで包まれる私に、貴方は寄り添い、私の身体を温めながら、七色のクロシェットを落としてくれる。
『知っていたんだよ。みんな、分かっていたんだ。』
優しい鳴き声で。私の頬にキスをして。
『僕達が愛したのは、過去の幻想じゃない。』
許しの言葉を、私にくれる。
『僕達の為に優しい嘘をついてくれた。僕らを癒したのは、他の誰でもなかった……七色のクロシェットを持つ、君なんだ。』
私は涙の流れるままに目を閉じる。全ては嘘を重ねただけの人生だと思っていた。けれど今。今、ようやく分かるのだ。
七色クロシェット、と。誰かが私をこう呼ぶだろう。私を愛した家族と私を愛した恋人が。
私はクロシェット。七色の名を持ち、この街で一番愛された。
私はクロシェット……七色の名を持つ、世界で一番、幸福な子猫だった。